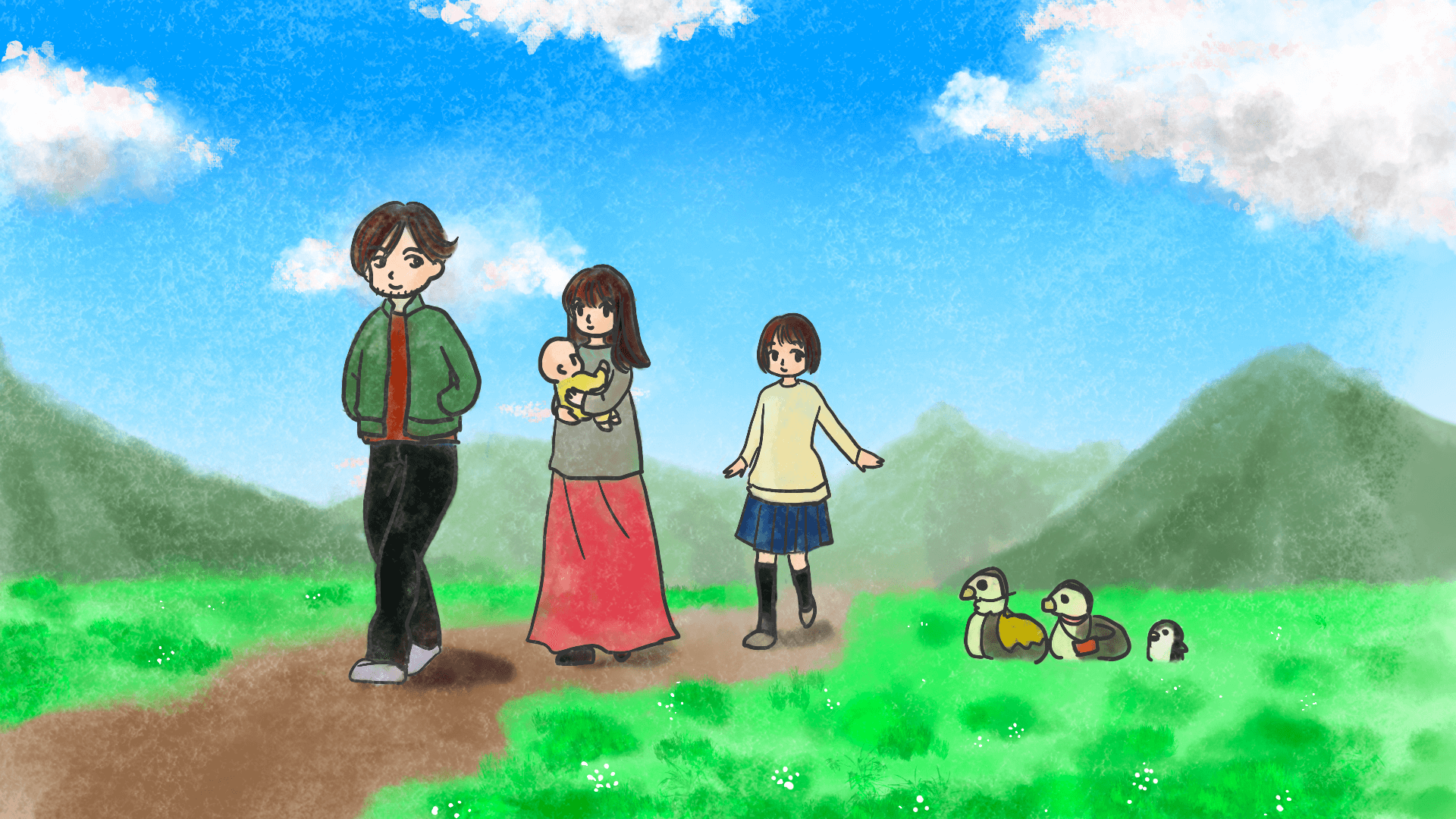ぬいぐるみ症候群とは
またの名をブランケット症候群ともいい、お気入りのぬいぐるみやブランケット、タオルなどに愛着し、手放せない状態のことを言います。
ぬいぐるみ症候群は珍しいことではありません。
実際小さい頃、お気に入りのぬいぐるみやブランケットがあったという人は結構多いのではないでしょうか?
実は私にも昔お気に入りのぬいぐるみがあり、どこに行くにも抱っこしていたみたいです。
あまりに抱っこしていたものだからボロボロになってしまい、見かねた両親が良かれと思い、全く同じものを新しく買ってくれたらしいのですが、私は新しい子には見向きもしなかったそうです笑。
私にとっては、そのボロボロのぬいぐるみが唯一無二だったんでしょうね。
残念ながら今となっては全く覚えていませんが、恐らくその頃の私はぬいぐるみ症候群だったのだと思います。
お気に入りのうさぎを忘れて大ピンチに
次女のさんごは出産祝いで貰ったうさぎちゃん(以降ピョン吉と呼びます)が大好きで、文字通り何をするにしても常に持ち歩いています。
お外に買い物や散歩に行く時もそうだし、お風呂の時はお風呂場の外で待っててもらっているし、寝る時は絶対抱っこして寝ます。
一度うっかりピョン吉を家に忘れたまま外出してしまい、途中で気付いたさんごが道端で大騒ぎしてえらい目にあいました。
ピョン吉の名を大声で叫び、往来でギャン泣きする娘…。
声は響き渡るし人の目は気になるし、たまたま持っていたマスコットを渡すも「これじゃない!」と拒否され途方に暮れました。
家を出発してかなり経っていたので、取りに戻ってまた家を出るのは面倒だし、最悪お出かけそのものをもう諦めようかと思いました。
しかし、その時さんごがペットボトルで遊ぶのにはまっていたのを思い出しました。
当時ペットボトルが大好きな時期で、家でペットボトルを見つけるとくれくれと強請られていたのです。
ちょうど泣き出した場所がコンビニの前だったこともあり、藁にもすがる思いでコンビニでペットボトルを購入して渡したところ、泣き止んでくれたのです。
こうしてなんとかその場を凌ぎましたが、いつまたピョン吉を思い出すか気が気ではなく、結局お出かけはそこそこに帰宅したのでした。
そしてもう二度とピョン吉を忘れてはならないと心に誓いました。
保育園や幼稚園には、ぬいぐるみを持っていけない
それほど彼女にとって大切なピョン吉ですが、集団生活をするにあたって連れていけない場所というのが出てきます。
そう、保育園や幼稚園です。
そのような他のお友達がたくさんいるような場所では、特定のぬいぐるみを連れて行くのはお断りされることがあると思います。
次女のさんごもプリスクール入学にあたり、体験レッスンでは黙認されていましたが、やはり正式に入学となるとピョン吉はお家で待っていてもらうように、と言われました。
しかし、ぬいぐるみは子どもにとって愛着の対象であり、不安な気持ちを紛らわす安心の基地なのです。
つまり両親の代わりのようなものでもあるので、無理矢理引き離すのはなんだか良くないような気もします。
こんな時、一体どうすればよいのでしょう。
ぬいぐるみやブランケットを卒業するには?
結論から言うと、卒業する必要はありません。
大切なぬいぐるみ、ブランケットで安心を得ることは、それ自体は問題行為ではないからです。
ただ、ぬいぐるみやブランケットを持っていけない場所があり、その時には離れることが必要になります。
スクールからの提案では、スクールの間は「ピョン吉はお家で待っているからね」とお話して、お家に置いてくるのはどうかと言われました。
しかしそう簡単には行きません。
毎回外出のときもいつも一緒だったピョン吉を、お話することではいそうですか、とそう簡単に置いて行けるのであれば苦労しないのです。
さんごは、ピョン吉は家で…と話をした途端泣き出し、ピョン吉なしには絶対に家を出ようとはしませんでした。
次の手段として、小さなシールを用意するのはどうかと提案されました。
小さなシールを服に貼り、ピョン吉の代わりになってもらうのです。
スクール側はなんとかさんごが自然にピョン吉を手放せるよう、色々案を出してくださり本当に有り難かったです。
そして結果的に、この案がうまく行きました。
ピョン吉に似たうさぎのシールを用意して、「スクールの時はこの子がピョン吉の代わりに一緒にいてくれるからね」と話したら、ピョン吉とシールを交換することに成功したのです。
そんなわけで、さんごはしばらくうさぎシールを貼り付けて登校していました。
今ではなにも貼らずに登校しています!
…と言いたいところですがそう上手くはいかず、今ではシールの代わりにキャラものがプリントされた服を着て登校しています。
キャラクターがピョン吉の代わりなのです。
さんごは不安を感じた時だけでなく、希望が通らなかったり、上手くできなかったりでイライラした時、服に描かれたキャラクターをぎゅっと握ることで気持ちを落ち着けていました。
さんごは他の記事でも触れていますが大変に気の強い意志のはっきりした子で、親としては扱いづらいと思うことも多いのですが、そうやって感情をコントロールしている様子を見たときは、幼いのに誰に教わるわけでもなく、なかなかすごいことをするものだと感心しました。
キャラがプリントされていない服の時には、やはりシールを欲しがります。
なにかピョン吉の代わりになるものがまだまだ必要なようですが、ピョン吉は一緒にスクールに行けないということは分かっているようで、家から出る時には一緒に行きますが、スクールに着くと自分から私にピョン吉を手渡してくれるようになりました。
これだけでも進歩かなと思っています。
執着と発達障害の関係は?
さんごのように特定のぬいぐるみやブランケットに執着するという行為は、幼い子どもにはよく見られることですが、あまりに執着が強いと、「これって発達障害では?」と不安になることがあるかもしれません。
確かに発達障害、とくに自閉症に見られるこだわりと似通っているように感じるかもしれません。
しかし自閉症のこだわりの強さは、ぬいぐるみ症候群のそれとは比べものにならないと私は思っています。
自閉症のこだわりは、特定のメーカーの特定の商品しか食べないだとか、全く同じ服ばかり着たがるとか、同じ道ばかり通るだとか、こだわりの範囲がすごく狭くて融通が効きにくいというのが特徴です。
そして、特定の物に執着するというよりは、習慣や行動に対するこだわりが強いです。
自閉症は変化に対する不安が強いので、同じこと、決まったことを求めるのです。
どちらも安心感を得たいという目的は同じですが、ブランケット症候群が安全の基地であり、発達上問題はなく多くの場合成長するとなくなっていくのに対し、自閉症のこだわりは、多少和らぐことはあっても無くなることはありません。
ですので、ぬいぐるみやブランケットに執着が強くても、あまり心配しないで大丈夫です。
大人のブランケット症候群
しかし中には、大人になってもぬいぐるみやブランケットが手放せない、という人もいます。
何を隠そう私の夫もその一人なのです。
うちには有名アザラシキャラのゴ◯ちゃんをはじめとするぬいぐるみが多数おりますが、みんな30歳を超えています。
彼らは夫が小さい頃に買ってもらった子たちで、なんと今でも一緒に寝ているのだから驚きです。
冒頭のマンガのゴ◯ちゃんは本人の色をなかなか忠実に再現していますが、恐らく発売当時の色とは全く違うと思います。
目は取れかけ、顔はボロボロでほとんどないようなものだし、中身のスポンジが漏れていたり、初見ではあまりの衝撃ビジュアルに驚きを隠せませんでした。
しかし、亡くなったおばあちゃんが買ってくれたからずっと大事にしている、なんて話を聞いてしまったからには悪くは言えません。
今でもゴ◯ちゃんは、大事な我が家の一員として元気に生活しています。
このような大人のブランケット症候群というのも割と多いようで、元歌のお姉さんのはいだしょうこさんも、小さい時からのぬいぐるみを今も大切にしていらっしゃるそうです。
ぬいぐるみの病院というのもあり、入院後は外科手術などの適切な治療を受け、綺麗になって退院できるそうです。
いかにぬいぐるみが多くの方達に愛され、家族同様の存在であるかがよくわかると思います。
入院費は高額なようですが、いつかはゴ◯ちゃんも入院できればいいなと思っています。